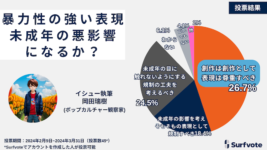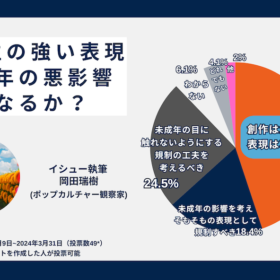1961年1月2日生まれ、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス出身。10代から映画に関心を持ち、高校時代に最初の短編『The Suicide』を製作、大学時代にはアルチュール・ランボーにインスパイアされた中編『Assassins: A Film Concerning Rimbaud』(85年)などを製作した。その後、ニューヨークに移り、88年にはバービー人形を使ってカレン・カーペンター(カーペンターズの妹)の最後の日々を描いた中編『Superstar: The Karen Carpenter Story』(88年)で注目される。ジャン・ジュネの小説「薔薇の奇跡」を原作とした長編デビュー作『ポイズン』を91年に発表。その後、『SAFE』(95年)、70年代グラムロックのスーパースターとなった青年を描いた『ベルベット・ゴールドマイン』(98年)、ダグラス・サーク監督の『天はすべて許し給う』(55年)にオマージュを捧げた『エデンより彼方に』(02年)、6人の俳優にボブ・ディランを演じさせてディランの半生を描いた『アイム・ノット・ゼア』(07年)と、アカデミー賞はじめ国際的に高く評価される作品を次々に生み出している。
映画『キャロル』は、50年代のニューヨークで運命的に出会った2人の女性の愛の物語で、「自分に正直に生きる」ことの意味を問いかける名作だ。
大ヒット映画の原作としてしられる「見知らぬ乗客」「太陽がいっぱい」などを手がけた作家パトリシア・ハイスミスが別名義で発表し大ベストセラーとなった小説を、独特な映像美で人気の鬼才監督トッド・ヘインズが映画化。ケイト・ブランシェットとルーニー・マーラの共演も素晴らしく、アカデミー賞にもノミネートされるなど話題を呼んでいる。
各国の映画批評家たちがこぞって絶賛する本作について、ヘインズ監督に話を聞いた。
監督:僕の作品の特徴は、ほとんどすべて設定が過去になっていることだ。でも、本作の舞台である1952年から53年は、『エデンより彼方に』の1957年とは全く違うと思うよ。
まず、あの時代のダグラス・サーク監督のメロドラマに強い興味があるんだ。現実の50年代には興味がなかった。興味があったのは映画の中の50年代だ。(『エデンより彼方に』の舞台となった)当時のコネティカット州ハートフォードの人たちが実際にどんなだったかはどうでもよかった。登場人物にLAのバックロット(撮影用の野外セット)から出て来たように見えてほしかった。
ニューヨークで撮影されたドキュメンタリー・ドラマはとても参考になったよ。当時のニューヨークは40年代後半から脱け出したばかりで、寂れてすすけた汚い町だった。ダグラス・サーク監督のホームドラマにある、キラキラした、エナメルを塗ったようなコネティカット郊外とは全く違う。だからこの2つは僕の中では別物だ。
監督:ああ、そうだけど、僕は当時の映画を見ていたんじゃない。当時の考証文献を見ていた。
見ていた映画は恋愛ものが多かった。映画の素晴らしいラブストーリーの中で、視点や主観性がどんな位置づけをされているかを見ていた。基本的に小説ではどんなふうにテレーズ(ルーニー・マーラーが演じた役)の視点に根差しているかを追っていた。テレーズの視点がとても好きだった。とても強いと思った。この企画を始めて脚本の手直しをする時は、ある意味、そこに戻っていた。
──記者会見などで監督は、「視点の変化」について語られていますが、その変化によって本当に表現したかったのは何でしょう? 愛する人と別れることをいとわない人間が最も力があるということでしょうか?
監督:通常、古典的なハリウッドの脚本では、男性の視点で女性が語られる。だが男性の視点は力と動きのある立場で、その対象は動かない立場だ。ストーリーは主役の行動を通して進み、主役がそのエンジンを持っている。しかし、愛が誰の視点で語られるかと言えば、弱者の方だ。弱者は相手を見つめ、相手が自分をどう思っているか、解明しようとしている。相手がすべての力を持っている。核心となる問題は、相手が自分をどう思っているかということ。答えを間違えば破滅だし、答えが正しければ解放される。完全に身動きの取れない状態だ。これがとても気に入った。
小説ではテレーズはこの状態で、それに加え、彼女は自分たちの愛がどんなものかを言葉で表すこともできない。一つの文で言うことすらできない。実際、小説の中にこんな一節がある。「私はこれを愛と呼ぶだろう、キャロルが女性だという点を除けば」。まるでこの愛には構文がないようだ。彼女は言う。「ショートカットで男物のスーツを着た女性たちを見たことはあるが、それは私らしくないし、キャロルらしくもない。だから、あれが私たちの真の姿であるはずがない」。世界には彼女の気持ちや望みを表す手本がなく、想像することすらできないのだ。
だが物語が進むにつれ、この立場は変化し、テレーズは変わってゆく。彼女はもう映画の冒頭の彼女ではない。そして、心を開放することがどれだけ大切かに気づいているのがキャロルなんだ。
監督:デヴィッド・リーン監督の『逢びき』かな。
原作を読んだ時、最初に考えたことのひとつに駅での同じシーンの再現があるが、これが興味深い。『キャロル』同様、映画の冒頭シーンでは、セリア・ジョンソンもトレバー・ハワードもエキストラのように背景にいて、彼らが何の話をしているのか、それがどういう意味なのか、観客には分からない。だが全体を見た後で、「あぁ、これは……」と気づく。観客は、まずこれが彼女の話であることを知り、それから彼女がクロスワードをやっている夫に心の中で何があったのかを語り、観客が冒頭シーンの意味を理解したところでそれがすべて再現される構成だ。『キャロル』でも同じアイデアを使っているが、それだけではなく、作品の視点が変わる。最初、マクガフィン(登場人物への動機付けや話を進めるために用いられる仕掛けのひとつ)にすぎない、明らかに本筋とは何の関係もない男の視点から始まり、やがて観客はこれがテレーズの物語になると気づく。だが映画の途中、視点が変わり、キャロルがテレーズを見る視点になることもある。その時は、キャロルがテレーズに一緒にいてほしいと思っているんだ。これが追加のひねりだ。

(C)NUMBER 9 FILMS (CAROL) LIMITED / CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 2014 ALL RIGHTS RESERVED
──50年代には女性同士の恋愛は犯罪とされていて、パトリシア・ハイスミスは実体験を基にした原作を実名で出版することができませんでした。それを踏まえると、本作はアメリカの歴史の一面を描いた作品だと思うのですが、政治機能、政治的意図は込められているのでしょうか? あなたはアメリカ人の監督ですが、この作品で少数派の人々の声を語る必要性を感じたんでしょうか?
監督:政治的、社会的偽善や抑圧はずっと興味を持ってきたことだ。たぶんもっと広い意味でも、自然で一貫した変わらないアイデンティティに対する抑圧も。だから……気づくと一日中、ブツブツ言っているな(笑)。
でもいい質問だ。だから、女性がテーマの映画に興味があるんだと思う。女性は男性より社会的プレッシャーや限界に苦しんでいる。女性の話を語ることは、社会的要素について考えることになり、それが僕にとっては政治的で重大なことだ。
NEWS
PICKUP
MOVIE
PRESENT
-
ユ・ヘジン&キム・ヒソン共演『マイ・スイート・ハニー』のオリジナルクリアファイルを5名様にプレゼント!
応募締め切り: 2024.05.05 -
【キャスト登壇】生田斗真×ヤン・イクチュンW主演『告白 コンフェッション』の完成披露試写会に10組20名をご招待!
応募締め切り: 2024.04.20