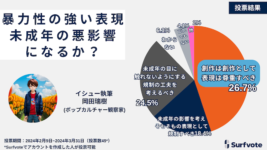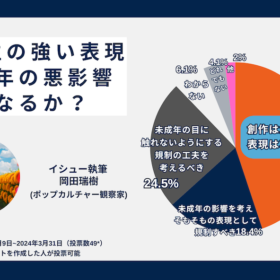コロンビア・ピクチャーズを経てハリウッド・レポーター誌国際版編集長をつとめた後、制作会社を設立。2012年に初監督作『MA PREMIERE FOIS』を制作。主な監督作は『奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ』(14年)、『ヘヴン・ウィル・ウェイト』(未/16年)など。また、プロデューサーやテレビ局スタッフ、ジャーナリストなどから成るフランス映画の女性サークル「CERCLE FEMININ DU CINEMA FRANÇAIS」を設立。
『パリの家族たち』マリー=カスティーユ・マンシオン=シャール監督インタビュー
母として、娘として自分の人生を模索する女性たち。共感で涙する感動作が公開!

仕事、子育て、結婚、年老いた母との関係……。女性大統領やベビーシッター、女優、花屋など様々な仕事を持ち生きていく女性たちが、自分らしい生き方を探し求める姿を描いた『パリの家族たち』。タレントのフィフィが「嗚咽が止まらない」と絶賛したことでも話題の作品が、5月25日より公開される。
監督のマリー=カスティーユ・マンシオン=シャールは、落ちこぼれ生徒と女性教師の感動の実話を映画化した『奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ』で高い評価を得ている。女性たちの繊細な心の内を温かなまなざしで描いた本作について、監督に語ってもらった。
監督:母性というテーマは、汲めども尽きぬ物語の源泉です。あまりにもたくさん物語があるので、群像劇にするしかないと思いました。私はこのジャンルの大ファンで、繰り返し見ては、見落としていた小さなディテールを発見して楽しんでいます。登場人物の接点や、シーン同士のつながりなどをですね。今回とくに探究してみたかったのは、育児に不安を抱える共和国大統領でもある一人の母親です。また、スペクトルのもう一方の端には、息子によりよい将来を保証するため、国を出て我が子と離れて暮らすことを選んだ中国人娼婦。母親の最も美しい埋葬を考える以外に母親とは関係がなくなってしまった主婦の娘。母の思い出と共に生きる息子。母親に対して過保護なユダヤ人の息子。母親との複雑な関係のせいで、母性に対して三者三様の関わり方をし、結局、母の日に母親を置き去りにする三姉妹。そして、すべての物語をつなぐ赤い糸として、「母の日」の由来が語られます。
監督:これまでのシナリオの時より長くかかりましたが、面白いプロセスでした。ジグソーパズルを立ち上げ、登場人物の軌跡を交差させ、群像劇という「合唱」の楽譜を想像する必要がありました。私はこの作業に幾度も向き合い、書き直す度にキャラクターの人物像を修正しなければなりませんでした。その最たる例は、たぶん女性大統領でしょう。(演じた)オドレイ・フルーロがOKをくれたバージョンから最終版までに、大統領の母親業との関わり方を3回も根本から変えました。シナリオの最終版がオドレイに届いたのは、クランクイン一週間前でした。シナリオは、人々との出会いや見聞きした話からも生まれるものであり、それが私の登場人物を育てます。その点、この母親というテーマについては、いくらでもストーリーがあります。しかも編集で、また一からやり直すことになったんですよ!
監督:母親讃歌を作るつもりはなく、また母親との関係のややこしさや、母親業への関わり方の難しさを過小評価したくありませんでした。あの生殖機能というものを、私は全く賛美していません。母親は、その地位によって、巨大な権力を持っていると思います。あらゆる権力は有害・有毒かつ破壊的となる可能性があります。そのことも扱いたいテーマでした。正直なところ、私には「母性本能」の意味が分からないし、それが実在するかどうかも知りません。自分の子どもができた時に初めて、自分の母とのつながりと、自分の母性に気づくのだと思います。母親であることは、ただ子どもを産むことよりずっと複雑だと思います。
監督:1人いますよ、脇役ですけど。バスの中で電話で「やめて。決めるのは、母親である私よ」と言う女性です。権力濫用と言ったのは、こういうことでもあります。大勢の母親がもっている、あの確信です。父親より自分のほうがよく知っていると。中には父親に出る幕を与えない人もいます。映画では、カルメン・マウラが見事に演じてくれた(シッターの)テレーズが、完璧な母親に近いように感じられます。それは、テレーズ自身の物語と母親業との関わりを通して伝わってくるはずです。テレーズは6人の子の母親で、深い愛情を注ぐけれど余計な口出しや干渉はしない。寛容さや自己犠牲、献身という美徳を備えているからです。彼女は誰にも評価を下さない。ただそこにいるんです。
監督:第一に、集合的無意識の中に何か痕跡を残すことができる余地があるとしたら、それは映画やテレビだからです。でも私はもっと踏み込見たいと思いました。私はいつの日か女性大統領が誕生すると確信していますが、その大統領が母親になった時、人々はどのような反応をするか見てみたいと思ったからです。今日でもまだ、女性は子どもを持つか、キャリアを選ぶかの選択を迫られることが多いのが現実です。社会はそのことをどう考えるのか? これらの選択をどのようにサポートするのか? 私は、この女性大統領を作品に登場させたかった。彼女は他の女性たち同様、母となったがゆえに、仕事だけやっていればよいというわけにはいかなくなります。私の関心は、そういった仕事と母親業の両立にあるのです。この問題については、すべてが解決したとはとても言えません。女性が母親業とキャリアのどちらも犠牲にせず、両立できるように条件と手段を提供するまでには全然なっていません。そして役割分担に関しては、まだまだ進歩が必要です。
監督:屋外についてはエリゼ宮の中庭とロビーです。共和国大統領と大統領府が撮影を許可してくれました。確かマクロン大統領はOKを出す前に私の作品を見てくださったはずです。ブリジット夫人が『奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ』をご覧になったことは知っていました。フランソワ・オランド前大統領は、退任前に官邸の住居部分の見学を許可してくださり、すごくためになりました。というのは、それがごく普通のオスマン様式のアパルトマンで、とくに広いわけでもないことが分かったからです。おかげで、適切な広さの同じようなアパルトマンで撮影できました。執務室のほうは、パリにある、大統領官邸風インテリアの個人邸宅で撮影しました。
NEWS
PICKUP
MOVIE
PRESENT
-
ユ・ヘジン&キム・ヒソン共演『マイ・スイート・ハニー』のオリジナルクリアファイルを5名様にプレゼント!
応募締め切り: 2024.05.05 -
【キャスト登壇】生田斗真×ヤン・イクチュンW主演『告白 コンフェッション』の完成披露試写会に10組20名をご招待!
応募締め切り: 2024.04.20