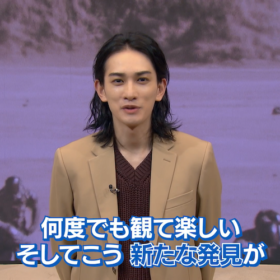1962年5月23日生まれ、イスラエルのテルアビブ出身。自主映画制作を経て、カメラマンやプロダクションデザイナーに。2009年に自身の徴兵体験をもとにした『レバノン』で監督デビュー、第66回ヴェネチア国際映画祭でグランプリ(金獅子賞)受賞。8年ぶりとなる『運命は踊る』(17年)では第74回ヴェネチア国際映画祭で審査員グランプリ(銀獅子賞)を受賞したほか、第90回アカデミー賞外国語映画賞イスラエル代表にも選ばれている。
敵と味方の区別すらつかない戦闘下で、狭い戦車内で若い兵士たちが極限状態へと追い込まれる様子を描いた衝撃作『レバノン』でヴェネチア国際映画祭グランプリ(金獅子賞)を受賞したサミュエル・マオズ監督。イスラエルに生まれ育ち、徴兵経験をもつ彼が、自らの体験をもとに8年ぶりに作り上げた『運命は踊る』が、先週末より公開された。
息子の戦死の知らせと、追って届いた生存の知らせ。誤報が招いた悲しみと喜びが交差するなか、運命の不条理が描かれていく。
イスラエルの右派政治家から「有害な映画」と非難される一方、アカデミー賞では外国語映画賞のイスラエル代表作に選ばれた本作について、マオズ監督に聞いた。
監督:遅刻癖のある娘が、寝坊をするたび高校へ行くタクシー代を請求してきて、ある日頭にきて、みんなと同じようにバスを使えと送り出しました。そのバスは、テルアビブの中心地に向かう5番線で、乗客も多い路線のバスです。娘が出てから30分後、彼女が乗ったはずのバスが自爆テロに巻き込まれたとのニュースが報じられました。
携帯で何度も連絡しましたが、回線がパンクしていて繋がらない。しかし、彼女は1時間後に無事帰ってきました。実際には、そのバスにも乗り遅れていたのです。私は壮絶で過酷なレバノン戦争も経験していますが、それらの経験をもってしても、娘を待つ1時間のほうがはるかに辛く、最悪な時間でした。
自分が良かれと思ってしたことが、娘を死に追いやったかもしれない。この体験をして、もしかしたらここから学びを得られるのではないかとも思いました。
「人生は偶然の産物なのか」「人は運命を司ることはできるのか、運命をコントロールすることができるとすれば、どんな代償を払わなければならないのか」と考えました。こうしたことが、この作品の根底にはあります。一方、娘はあの経験を経ても、結局遅刻癖は治りませんでした(笑)。もう一つの学びは、小さな欠点は受け入れるべきだということです。欠点を是正すると、その人が持つ良い部分も変容してしまうのではないか。そうだとしたら、家族や、まわりの人の小さな欠点は受け入れるべきだとも思いましたね。
監督:『レバノン』は、私が体験した戦争体験に基づいています。本当に過酷な経験でした。戦車に乗っていると、民家に分け入って入っていき、2軒に1軒はテロトリスとがいるから射撃しろと言われます。シャッターは閉まっているから確かめようもないのですが、2、3秒のうちに、自分も相手の人生も大きく左右するような判断をしなければならない。当然、モラルなど通用しない。あっという間に生死が分かれる世界。戦地に送り込まれて24時間を超えても寝ることもできない、異様な神経になっていくんです。そうした経験を経て作った『レバノン』では、戦車のスコープから覗いているような構造になっていて、観客も追体験するかのようなヴィジュアル的なものを描きたいと考えていました。私は、あの酷い戦争を経験してPTSDとまではいきませんが、トラウマをかかえてしまいました。日常生活は問題なく営めても、常に沸々としたものがずっと心に残っていたんです。
デビュー作が40代というのは、遅いといわれますが、逆にいうとそれくらいの年齢でないと駄目だったんです。『レバノン』は各国の映画祭で高い評価をいただくことができました。それまではどこかで、自分はずっと「独りぼっちだ」という感覚がありましたが、その時に初めて、そうでないと思えました。同じような経験をした人は周りにもいるのだと。
そこからイスラエルを描こうと思ったんです。イスラエルはトラウマを抱えた社会です。ホロコーストを経験し、レバノン戦争を経験し、世代から世代へとトラウマを受け継いでいます。これまでイスラエルは、まるでフォックストロット(※)のダンスのように、負のループから抜け出せずに同じところに戻ってきてしまっていました。最新作『運命は踊る』では、そうした社会が抱える問題を、“ポストトラウマを抱える個人ストーリー”として描きたいと思いました。その個を通して、家族の離散、そして修復。人は痛みを抱えてどう生きるのか。愛情は人を罪悪感から救い出してくれるのか……といった普遍的な要素を映し出したいと思ったのです。
もしかしたら、運命は変えることができないのかもしれません。しかしそれは神の思し召しなどではなく、人間の在りようがそうさせていると思います。トラウマを負ったイスラエル人の歴史や、人々に刷り込まれた意識が、負のループからの変化を拒んでいるのかもしれません。まるで、70年の刑期を終えた囚人が、どのように自由を謳歌していいかわからないかのように。しかし、この『運命は踊る』は、そこから一歩踏み出せるかもしれないという、一縷(いちる)の希望を持たせてくれるような作りの映画になっています。
(※FOXTROTは、1910年代はじめにアメリカで流行した、4分の4拍子、2分の2拍子の社交ダンスのステップを指す。本作の原題でもあり、「前へ、前へ、右へ、ストップ。後ろ、後ろ、左へ、ストップ」で、元の場所に戻って来る。どうあがいても、いくら動いても同じところへと帰って来る。動き出した運命は変えることができないということを象徴)
監督:ミハエルは、私と同じ世代の設定です。彼はホロコーストの生き残りである母親に育てられました。聖書は代々、家族を繋ぎ守ってきましたが、時代は変わり、聖書はその役割を終えた。ミハエルは、今までとは違うやり方、ダンスでトラウマから抜け出そうとしたのです。それは宗教や思想ではない。自分は新しい「生」を生きるのだと。そうした「生」をエロ本が象徴しています。しかし、ミハエルは結局別のトラウマを引き続くことになってしまいました……。それは、あたかも自分たちがはじめた戦争の代償を30年後に子どもたちが払っているかのようです。物語の中で、息子のヨナタンは、そうした父が表にあらわさない動揺や弱さを理解していました。最後に、そのことにミハエルも気づきますが……。
NEWS
PICKUP
MOVIE
PRESENT
-
ユ・ヘジン&キム・ヒソン共演『マイ・スイート・ハニー』のオリジナルクリアファイルを5名様にプレゼント!
応募締め切り: 2024.05.05 -
【キャスト登壇】生田斗真×ヤン・イクチュンW主演『告白 コンフェッション』の完成披露試写会に10組20名をご招待!
応募終了: 2024.04.20