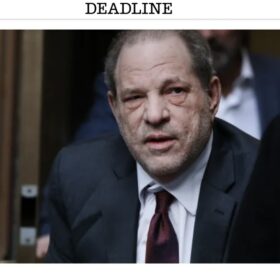1996年4月16日生まれ、福岡県出身。2011年に英勉監督の『高校デビュー』で映画デビュー。主な出演作は『オオカミ少女と黒王子』(16年)、『ルームロンダリング』(18年)、『SUNNY 強い気持ち・強い愛』(18年)、『貞子』(19年)、『騙し絵の牙』(21年)、 Netflix オリジナルドラマシリーズ『FOLLOWERS』(20年)など。2020年には、『夏、至るころ』で映画監督デビューを果たしており、今後も幅広い活躍が期待されている。
自分でレールを敷き続けていくことに必死だった
女優だけでなく、執筆業やモデル業、歌唱力の高さでマルチな才能を発揮している池田エライザ。24歳という若さながら、キャリアはすでに10年以上を誇っており、今後も幅広い分野でのさらなる活躍に注目が集まっている。そんななか、今年は『夏、至るころ』で満を持して映画監督デビューを果たした。
劇中では、翔と泰我という2人の男子高校生と不思議な少女・都がさまざまな葛藤を抱えながらも、成長を経験するひと夏の様子を福岡県の田川市を舞台に描いている。本作が誕生したきっかけは、「地域」「食」「高校生」をテーマにした青春映画制作プロジェクト「ぼくらのレシピ図鑑」シリーズの企画との出会いによるものだが、池田は自身でワークショップなどを実施しながら丁寧に作り上げていった。そこで、初監督を終えたいまの心境や映画を通して伝えたい思いについて語ってもらった。
池田:以前からやりたいと言ってはいましたが、お話をいただいたことによって改めて感じるプレッシャーは当然のことながらすごく大きかったです。ただ、やると決めてからは、次にやらなければいけないことや目標が多すぎて物怖じしている暇はなかったですね。
池田:いつの間にかそう思うようになっていたので、自分でもわからないんですけど、本当に自然と、という感じです。ただ、小学生のときから小説を書いていたり、文芸誌でエッセイなどを書かせていただいていたりもするので、思いついたものは短編小説やプロットとしてたくさん書き溜めるようにはしています。
池田:この作品には、田川市の町おこしという意味もあるので、まずは2018年の12月にシナリオ・ハンティングで現地を訪れました。そのときに10代から親世代まで、それぞれ数十名ずつ集まっていただいて、座談会をしたんです。そこで聞いた言葉だったり、みなさんの田川市に対する思いだったりを聞いてゼロから作りました。
池田:これは田川の面白いカルチャーだと思いましたが、どこにいってもほぼ全部大盛り。「部活やっている高校生でもこんなに食べられないよ!」ってくらい出てきますからね(笑)。でも、それが田川らしさなのかなとも感じました。ちゃんぽんや皿うどん、山賊鍋という鍋料理までどれもおいしかったです。
池田:清純派女優みたいなこと言いますけど、学生時代は門限7時を守るタイプだったので、福岡出身なのに地元のグルメはほとんど食べたことがなくて、お母さんのご飯しか食べていないんです(笑)。でも、お母さんのご飯がおいしすぎるんですよ。近くに住んでいるので、いまでもたまに作ってもらっていますが、お母さんの料理で好きなのはポン酢で食べる春巻きです。
池田:高校3年生は、急に大人になることを求められたり、初めて自分について考えたりする時期。社会なんて見たこともないのに、そこでどう自分が立ち振る舞うべきかを考えさせられたりして、私は無理があるなと思っていたんです。なので、手を差し伸べると言ったらおこがましいですけど、一番声をかけたくなる世代かなと思って作りました。
みんなが前に進み続けているなかで、「この先には幸せがあるんだっけ? てか、そもそも幸せって何だっけ?」みたいに、生まれて初めて立ち止まった瞬間に初めて自分のいる場所を思い知るんですよね。だから、設定は王道でいいんじゃないかなと思いました。
池田:それは全然なかったですね。あのときは「CanCam」の専属モデルとかをしながら、自分で一生懸命レールを敷き続けていくしかなくて、彼らみたいに自分の本質について考えたりはできていなかったので。それよりも、「どうしたら“池田エライザ”をたまごっちのように育てていけるだろうか」ということに必死で、自分の心が動く瞬間に気が付いてあげられなかったという感じでした。そういう意味では、彼らがうらやましくもあります。
池田:自分が伝えたいことは入れているので、全部の役にそういうところがあるとは思います。たとえば、私も都のように悔しい思いを抱いていたことがありましたから。でも、さいとうなりちゃんがそれを100%の怒りでお芝居してくれたので、うれしくて私の怒りが成仏するのを感じました。ただ、恥ずかしいので、見ているときにそこはあまり意識しないで欲しいです(笑)。
池田:彼らの深いところにある気持ちをカメラの前で出して欲しいと思ったので、それを心地よく表に出してもらうためにはどういう言葉を選べばいいのか、どういう温度感で接してあげればいいんだろうか、というのは本番までの関係性を作る過程で意識しました。もちろん、監督としてこういうふうに演じて欲しいというビジョンもありましたが、第三者が台本を読んで感じたことも正解だと思うので、そこの折り合いのつけ方には苦労しましたね。うちのキャストたちは本当に素敵な瞬間をさらけ出してくれたので、それがみなさんの目に触れるのはうれしいです。
「日本映画がつまらない」と言うくらいなら自分で撮りたい
池田:自分がお芝居をしているときは、「もっと応えなきゃ!」とか「まだできたはず!」という思いがつねに付きまとっているものですが、今回の現場で演者たちのお芝居を見ていて、「自覚はなかったけど、俳優ってこんなにも人に影響を与えるいい仕事なんだな」ということには気付かされました。自分次第ではありますが、この経験が今後演者としても生かせたらいいなとは思っています。

『夏、至るころ』撮影中の池田エライザ監督
池田:ありましたね。やっぱり映画が好きなので、いろんな名作のシーンにオマージュを捧げたいとか、技術的にこうしたいとか、いろいろと思うことはありましたから。ただ、この作品ではそういう自分の“アート欲”みたいなものを一旦全部捨てる必要があったので、それが大変でした。もちろん、初監督作品で尖りを見せたい願望や自分の感性を褒められたい気持ちもありましたけど、今回はそれよりも丁寧にラッピングしてプレゼントする感覚に近かったです。
池田:まず田川市の方々には、改めて自分の街を誇らしく思っていただきたいですね。それぐらい素敵なところですから。ただ、映画を観てくださる方に対して操作は一切したくないので、観たあとに5分でも10分でも自分のことをいたわる時間にしていただけたらいいなとは思います。
池田:大切にしたいと思う人と一緒に仕事をしていることです。スタッフと「一緒に稼ごう!」なんて冗談でよく言っていますが、私の夢は自分のマネージャーさんとヘアメイクさんをいい家に住ませること。その気持ちは守り続けたいと思います。あと、子どものときにしたいと思っていた夢を忘れてしまうことが私にとっては一番悔しいので、自分が叶えたいと思ったことは時間をかけてでも、少しずつ叶えていきたいです。
池田:これまでガツガツ仕事だけをやってきましたが、ここで一回みんなにお礼を言わないと、次をがんばれないような気がしています。いままでは需要もないだろうと恐縮してイベントとかできずにいたんですが、「最近は私でよければ何かできることはないですか?」と事務所に相談するようになりました。あとは、仕事ばっかりで友だちともほとんど出かけたことないようなところがありましたが、少しずつ自分の人生も大事にできるようになってきたように感じています。
池田:いままでは、お芝居に没頭して周りが見えなくなってしまうところもありましたが、客観的に自分を見たときに、それをしなくても仕事を楽しめることに気が付いたんです。そんなふうに、冷静になってからはもっと自分を大切にしようと思えるようになりました。
池田:普段、私は悪口を言わないんですが、それが全部作品になっている感じなのかなと。たとえば、ニュースを見ていろんな気持ちになると思いますが、そういうこともすべて作品に生かしたいなと思っています。私は「いまの日本映画ってつまんないよね」と言うくらいなら、自分で撮ろうという性分。自分のことをクリエイターだなんて思ってないですし、好きでやっているだけですが、そういう思いがクリエイティブなことに繋がっているのかなとは感じています。
池田:今は気を抜いていたら周りに流されてしまうような仕組みになってしまっているので、自分を保つためにも、つねに自分が考えるべきことと向き合い続けるようにしています。そうしないと、目まぐるしい世のなかで、大切なものを置いてけぼりにしてしまうんじゃないかなと思うので。それに、自分の発言にちゃんと自分の意志を通していないと人もついて来ないので、そういうところは意識しています。
池田:そうですね。私はもともと気弱なところがあるので、人にお願いしたり、説得したりするときも、勢いだけでは行けなくて、きちんと伝えられる準備をするようにしています。映画を作るなら、「こういう方々に見ていただきたく、こういう気持ちになっていただけたらうれしいので、こういう映画を撮りたく存じます」みたいな感じで(笑)。見た目から、「池田エライザ、バーン!」というふうに思われがちなんですけど、そう見えるからこそ芯はちゃんと持っていないといけないなと思っています。
池田:これからも社会風刺であることは変わらないと思いますが、映画の難しいところは、作り始めたころの社会情勢に合わせていたら、完成したときには違う時代になっているかもしれないところなんですよね。そのためにも、なるべくいろんな方の意見を聞いて、未来を想像して作っていけたらいいなと考えています。
池田:手抜きになるのだけは嫌なので、まずはいまやらせていただいていることをしっかりとやり抜きたいですね。そのうえでみなさんに面白がっていただけるような新しいこともやれたらなと。ファンの方々にも楽しんでいただけるようなことができたらいいなと思っています。
(text:志村昌美/photo:小川拓洋)
NEWS
PICKUP
MOVIE
PRESENT
-
ユ・ヘジン&キム・ヒソン共演『マイ・スイート・ハニー』のオリジナルクリアファイルを5名様にプレゼント!
応募締め切り: 2024.05.05 -
【キャスト登壇】生田斗真×ヤン・イクチュンW主演『告白 コンフェッション』の完成披露試写会に10組20名をご招待!
応募終了: 2024.04.20