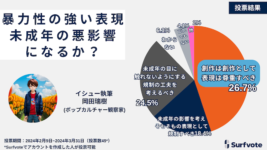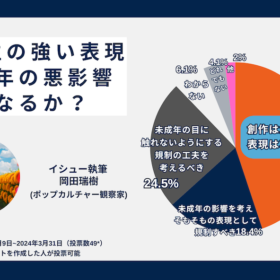1971年9月2日生まれ、ドイツのベルリン出身。女優として活躍、ロックバンドを結成した4人の女囚たちを描いた『バンディッツ』(99年)の美女役で注目を集め、『トンネル』(02年)など多数の作品に出演。2000年から監督業に進出。本作では脚本も務めている。
無機質な毎日を送る女性が野生のオオカミに惹かれ、愛し始める姿を描いた『ワイルド わたしの中の獣』。美しい女性が欲望をあらわにし、まるで本当の恋人のようにオオカミと愛を交わす描写が大きな話題を巻き起こした。
監督は、90年代に日本でもヒットしたドイツ映画『バンディッツ』で美女のエンジェルを演じた女優のニコレッテ・クレビッツ。世間のルールに逆らった主人公が日常から解き放たれ、官能的な世界に踏み出していく本作について、クレビッツ監督に聞いた。
監督:主人公・アニアは仕事へ向かう途中、マンションの前に広がる森で一匹のオオカミと出会います。この“野性”との出会いが彼女の中の“何か”を目覚めさせます。それは彼女が仕事や家族との生活の中でこれまで感じたことのない気持ちでした。アニアはもう一度そのオオカミに逢いたくて、彼を待ち、餌で釣ろうとしますが、次第にハンターと化していきます。そして、麻酔で意識を失ったオオカミを連れて帰り、自分の部屋に閉じ込めます。彼女は次第に野性化していき、全ての物事において野性的なアプローチを始めます。そして、その変化を彼女の周りの人間は楽しんでいるように見えます。日常から解き放たれたいと切望する彼女の想いに周りの皆が惹きつけられていくのです。
監督:自分自身の夢から思いつきました。怖い夢でしたが、そこに“オオカミ”がいたのです。そこから着想を得て、自分の住む世界というものを改めて考えてみました。そして、映画を撮影するのに困難な今回の設定をあえて選びました。
また、丁度その頃、オオカミがポーランドの国境を越えてドイツに来ているというニュースがありました。ドイツからはオオカミが消えて100年以上経っていますが、彼らはすごく魅力的な動物だと思います。上手く環境に慣れる、順応できるという点ではある意味人間に近いですね。だから自分たちの習性を長年変えずにここまで生息できたのです。野生を捨てずに来た、つまり“自由”を手放すということはなかったのです。そのオオカミ達がドイツという都会に戻ってきた。丁度そのタイミングで夢を見ましたから、そこがこの話の骨格になりました。
監督:本作は今までの「女性としてこうあるべき」といわれてきたイメージを全部壊す作品です。だから、映画館から出てきたときにとても良い気持ちになれると思います。ドイツで公開された時も皆さんがそのように思ってくれたのは嬉しかったです。男性の観客も含めて、私の意図は伝わったと思います。映画館にはカップルで見に来た人が結構いて、うまいこと2人の関係をいい方向へと向けてくれたと思います。私たちは「欲望」を持っています。それは男女に共通することだと思います。日本の観客の皆さんもそのように感じてくれたらいいなと思っています。
監督:この映画はものすごく用意周到に撮られています。つまり、安全をきちんと確保していました。まず、ハンガリーからオオカミのトレーナーを呼び寄せました。そのトレーナーにオオカミとの撮影はどこまでが可能なのかを色々と相談しました。オオカミが主人公を見て喜ぶ様子などを撮りたかったので。撮影は全部で28日間、1日の撮影は10時間くらいで、その内オオカミの撮影は15日間で1日3〜5時間でした。主役のリリト(・シュタンゲンベルク)は撮影前の3週間ハンガリーに行き、オオカミトレーナーの下で指導を受けました。そして、撮影は一匹のオオカミ(ネルソン)でほとんど撮影しました。
オオカミはあまり長く檻から出しておけません。オオカミと上手く撮影する秘訣は、オオカミをそこそこお腹いっぱいにしておくことです(笑)。舐めるという動作ではフォアグラを利用したり、リリトの後を付いていくシーンではポケットに肉片を忍ばせて少しずつ落としていったりしました。基本的にエサにつられればなんでもやりますね。しかし、オオカミは絶対に自由になる機会を見逃さないのです。もし檻の扉を少しでも長く空けていたりすれば、その隙に出て行って二度と帰ってこないでしょうね。犬とは違います。そもそも人を喜ばせようとは思ってないですし、どうでもいいんですよね。そこが彼らの魅力でもあります。だからリリトは本当に危険に身を晒しながら撮影をしていました。
監督:私たちは皆、生まれた時は野性的で、私たちのどこかに野性的なままでありたいという気持ちが残っていると思います。直感に正直に生きたいという想い。そして自分で選ぶ人生。もちろん都会でも野性的でいることは可能ですが、かなり難しいですよね。他人が貴方に対して思うこと、他人の評価は多くの場合、自分自身の声より正しいと思います。声とは、私たちの内側の声、非理性的で、道徳に反し、本能的な声です。私たちはどこかで自由を求めています。でも現実にはどれくらいの自由が許されているのでしょうか。自分の財産、他人からの評価など日々浪費して過ごしているけれど、それはあなたにとって無意味なことです。そして自分に何が一番必要かを完全に忘れてしまっているのです。
監督:そうですね。最終的に性別はあまり関係ありません。日常から逃避する手段は限られています。趣味、不品行、セックス……それらはすべて代替手段です。私自身も成人女性として、母親として期待されている通りの行動から逸脱したい衝動を持っています。それは決して口にはできないような内容です。周りに良い印象を与え、お金を稼ぐためにどうすべきかを心得ていますけれど、そんなことよりも、いっそのこと目的を持たずに生きてみたいです。未来は予測不能だからこそ、私たちは何も抑制するものがない自由な経験をしたいと感じています。私たちが内に秘めた欲望は時に衝撃的なものだったりするのです。
監督:私は皆さんに“経験”というものを提供したかった。大抵、他の似たような系統の映画だと、“自然に還る”ということは何らかの罰を与えられたりしますよね。コントロールが無くなった状態というのは、すごく怖いです。けれど何かに縛られない、制御されないというのは良いことなんです。私はそれを体感できる映画を作りたかったのです。
NEWS
PICKUP
MOVIE
PRESENT
-
ユ・ヘジン&キム・ヒソン共演『マイ・スイート・ハニー』のオリジナルクリアファイルを5名様にプレゼント!
応募締め切り: 2024.05.05 -
【キャスト登壇】生田斗真×ヤン・イクチュンW主演『告白 コンフェッション』の完成披露試写会に10組20名をご招待!
応募締め切り: 2024.04.20