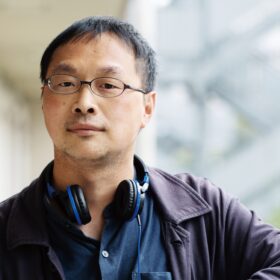肘鉄やドロップキックが当たり前の現場「仕事が出来ない自分が悪い」から目覚めたきっかけは…?
#MeToo#日本映画界の問題点を探る#日本映画界の問題点を探る/世界標準から周回遅れの状況を変えるために#深田晃司
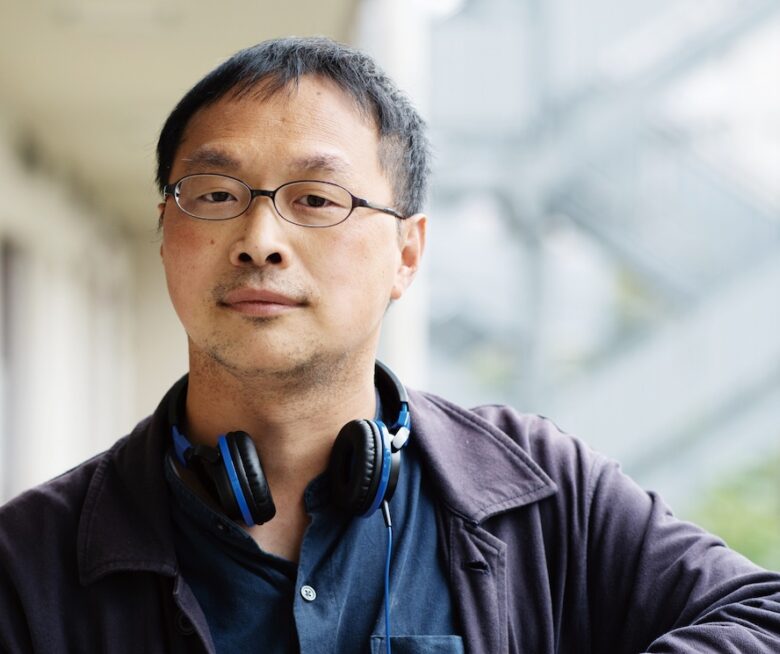
フランスの状況を知り、衝撃を受けた!
【日本映画界の問題点を探る/世界標準から周回遅れの状況を変えるために 1】2022年の日本映画界は世界から遅れてやってきたMeToo運動によって大きく揺れ動いたが、今年も引き続き業界が取り組むべき重要課題の一つと言えるだろう。そんななか、いち早くハラスメント問題に対して声を上げてきたのが深田晃司監督。2019年には、ハラスメントに対するステートメントを発表し、一石を投じている。その背景には、自身の体験が大きく関わっていると明かす。
「映画美学校を出た後、プロの現場を経験したほうがいいと思い、照明部や美術部に入りました。特に美術部のときの助手の先輩がとにかく怖い人で、怒鳴られる、なじられる、殴られる、肘鉄やドロップキックが飛んでくる、というのは日常茶飯事。ほかの部署の人たちからも、今から思えばモラハラや人格否定と思える扱いがたくさんあったのだろうと思います。でも、当時は仕事ができない自分が悪いと思っていましたし、映画業界はこういうものだと思っていたんですよね。その時期は、つらい現場に当たるととにかく耐え忍ぶという生活を繰り返していましたが、もともと監督希望だったので、自分で自主映画を作り始めるようになってスタッフの仕事からは離れて行きました」
そういった固定概念が変わるきっかけとなったのは、バイト先でたまたま出会ったフランス帰りのアーティストから話を聞いたとき。海外と日本の現場に、大きな差があることを知り、衝撃とカルチャーショックを受けたという。
「お互いの現場を手伝うようになってから、フランスの現場について教えてもらいましたが、あまりにも日本と違う。『怒鳴る人っていないの?』という驚きから始まったほどでした。ほかにも、労働時間がきちんと決められていることやフリーランスのスタッフに対しても社会保証制度が整っていることを知り、自分の当たり前は当たり前ではないのだなと。実際には怒鳴る人がまったくいないということではないと思いますが、それでも日本とは全然違う。僕自身も海外の映画祭に呼ばれることが増えるなかで、海外と日本の状況があまりに違うことがわかったので、徐々にいろんなことに気が付かされました」
・性的シーンで震える生身の俳優たち、守るための取り組みは始まったばかり
何十年も前からあった被害が露出しただけ
では、さまざまな経験と知識を得たいま、深田監督の目に現在の日本映画界はどのように見えているのだろうか。
「遅ればせながら日本でもMeToo運動の波が来たと言われていますが、ここで起きている被害や痛みは急に始まったことではなくて、もともと何十年も前からあったこと。被害と思われていなかった被害も数多くあり、自分の弱さだと思い込まされて業界を辞めていった方もたくさんいたと思います。それがようやく『これはおかしいんじゃないか』と言えるようになり、社会もそれを認識できるようになっただけ。これまで隠されていたものがやっと見えるようになってきたので、ここで変わらなければ、変わるチャンスをずっと失い続けてしまうと考えています。そういう意味では、良い方向に進んでいるところではないでしょうか」
本連載では、深田監督とも縁の深いカメラマンの芦澤明子氏にも取材しているが、その際に「俳優だけではなく助手クラスのスタッフにまで気を遣えるのが深田監督。その姿勢が、いま起きている運動の原点になっている」と話していた。そのことを伝えると、「身に余る光栄です」と謙遜していたが、自身の現場でも改善すべきことはあるという。

2014年に開かれた『ほとりの朔子』記者会見の様子/左から深田晃司監督、二階堂ふみ、杉野希妃(プロデューサー)
「僕の場合は、映画学校に入ったときからたまたま周りに年上が多く、とりあえず敬語で話すような習慣がついてしまったので、いまでも現場では基本的に誰が相手でもだいたい敬語で話します。ただ、特に心がけているのは、できるだけ全員に対して同じ態度で接することです。スタッフのなかには監督に対する態度と、助手や年下のスタッフたちに対する態度があまりにも違う場合があって困惑しますし、残念です。みんな優しくてうまくいってると思っていたのに、後から、裏で泣いている人がいたと知ることもあります。監督という権力勾配の高い立場にいる限り、どうしたって現場を隅々まで知ることは難しく、自分の現場が安全だなんて自信を持っては言えないですし、むしろそう断言する組織ほど危ないとさえ思っています」
とはいえ、そういった危機感を抱いているからこそ、実際にさまざまな意識を持って現場に挑んでいる。
「過去に自分の現場でハラスメントが起きてしまったこともあったので、それを無くすために、あるときからハラスメントに関する注意喚起を撮影の前に行うようになりました。これまでは自分なりの方法で続けていましたが、最近は専門の方に来ていただいてハラスメント講習をしてもらっています。それだけでいきなり問題がゼロになったりはしませんが、大事なのは積み重ねていくこと。自分自身の行動も含めて、今後も続けていきたいと考えています」(text:志村昌美)
PICKUP
MOVIE
INTERVIEW
PRESENT
-




【トークイベント付き】『エターナルメモリー』の一般試写会に10組20名様をご招待!
応募締め切り: 2024.08.09 -




【トークイベント付き】『コンセント/同意』の特別試写会に10組20名様をご招待!
応募終了: 2024.07.14