性別は“男性”…しかし女の子として生きたいサシャの意思に共感の嵐!
#HARU#LBGT#LGBT映画祭#イシヅカユウ#シカゴ国際映画祭#セバスチャン・リフシッツ#トランスジェンダー#フランス#ブレイディみかこ#ベルリン国際映画祭#モントリオール国際ドキュメンタリー映画祭#やまじえびね#ゆうたろう#ゆっきゅん#リトル・ガール#今日マチ子#合田文#売野機子#多田由美#大澤実音穂#小原ブラス#小林啓一#小林祐介#小田香#小谷実由#少年アヤ#映画賞#東京国際映画祭#楠本まき#池辺葵#相川千尋#福岡南央子#草野絵美#遠藤まめた#長島有里枝#長田杏奈#雪下まゆ

(C)AGAT FILMS & CIE – ARTE France – Final Cut For real - 2020
11・19公開『リトル・ガール』各界著名人から応援コメント&描き下ろしイラスト
「わたしは女の子」──言葉少なに訴えるサシャの真っ直ぐな瞳と強い意思が、見る者の心を震わせるドキュメンタリー映画『リトル・ガール』が11月19日より、全国で公開される。
この度、同作の公開を前に、モデル・俳優のゆうたろう、ライターのブレイディみかこ、モデルのイシヅカユウ、歌手のゆっきゅんら各界著名人からの応援コメントを寄せたほか、漫画家の池辺葵や楠本まき、やまじえびねらから、サシャへの思いを寄せた描き下ろしイラストも到着した。
サシャは2歳を過ぎた頃から自身の“性別の違和感”を訴えてきたが、社会は彼女を“他の子ども”と同じように扱えずにいた。
やがて7歳になってもありのままに生きることができない、不自由なサシャ。家族はそんな彼女の個性を支え、周囲に受け入れさせるため、学校や周囲へ働きかけるのだが……。
本作はさまざまな社会の壁に阻まれながらも、まだ幼く自分の身を守る術を持たない彼女の幸せを守るために奔走する家族とサシャの“ゆずれない闘い”を映し出した、心震えるドキュメンタリーだ。
モデル・俳優のゆうたろうは「我慢してきた感情が、ひとつの言葉によって溢れる涙に変わる少女を見て、抱き締めたくなりました。過去の固定概念で押し潰される未来たちがこれ以上増えないよう、いろいろな当たり前が認められる世になればいいなと思います」と語った。
ライターのブレイディみかこは「現実は小説よりも奇なり」というが、この映画を見て思った。ドキュメンタリーはフィクションより美しい。これは子どもに自分自身でいさせようとした親の闘いの記録だ。戸惑いながら自分にかけられた呪いを解く人だけが、周囲の呪いを解くことができる」。
モデルのイシヅカユウは「母と学校や診療内科に行って話し合った日々を、この『リトル・ガール』を見て、昨日のことのように思い出しました。あの頃、毎日溺れそうになりながら必死で泳いで今があります。この映画に寄り添うドビュッシーの音楽のように、この映画が心の性の違和に悩む人たちに寄り添ってくれたらと思います」と振り返った。
歌手のゆっきゅんは「幼くして聡明で優しいサシャは、初めから自分が何者であるか知っていたし、間違っているのは不寛容な社会の側であるとわかっていた。それでも、これからもきっと何度もふがいない涙を流すことになる。ただ自分自身としてあり続けることにおびえなくていい、あのラストシーンのような、そんな世界に少しずつなりますように。人生のセンシティブな一場面がこうして届けられたからには、早急に」と願う。
彼女へ語りかけ、勇気づけるメッセージが続々!
他にも、各界の著名人からの思いがあふれる応援コメントが到着した。
また、漫画家の池辺葵や楠本まき、やまじえびねらからはコメントと同時に、サシャをイメージした描き下ろしイラストを特別に公開。いずれもそれぞれの視点で彼女へと語りかけ、勇気づけるようなメッセージとなっている。
■長島有里枝(写真家)「サシャと家族は互いに支えあい、守りあっている。彼らがごく“普通”の人々であることは、彼らと似た境遇の人を励ますだろう。わたしの家族も、自分が誰なのかはその人自身が決めていいと考える“普通”の人たちだった。ありのままの誰かを理解し受け入れるために、ありのままの自分も認めて好きになろう。ちっとも難しいことなんかじゃないと、わたしは思いたい」
■楠本まき(漫画家)「サシャが青い服を全部処分することにした時『女の子も青い服を着るけど』と言ったサシャの母カリーヌ。彼女は痛いほど考えている。学校やバレエ教室との闘いに加え、未来を左右するだろうホルモン治療の決断までサシャのかわりにしなければならない。そのプレッシャーはどれほどだろう。彼女たちがこれ以上よけいな消耗をせずにすむように。優しい世界になるように。世界のひとりである私たちの考えるてがかりをリフシッツ監督はそっと差し出している」

楠本まきによるイラスト
■小原ブラス(タレント、コラムニスト)「何でこんなシンプルなことのために、ここまで戦わねばならないんだ。『寛容な社会』『多様性の社会』そんな言葉が流行っているが、寛容とは何か、この映画はエグる。なぜ、自分が自分であることを誰かに説明しなければならないんだ。何も反省することがないのに自分を変えなければならないのか。こんな重荷を子供に抱えさせてしまっていいのだろうか。未来の子どもたちにはこの苦しみを微塵も感じさせたくない」
■少年アヤ(エッセイスト)「変革の使命を背負うのは、ちいさな彼女でも、その家族でもない。もはや誰ひとりとして自由ではいられない社会を、のうのうと生きる私です。私たちです」
■売野機子(漫画家)「私たちは、どうして無意識のうちに娘の髪を直すんだろうね。パパとママの手が、事あるごとに脈略もなくサシャの頭に伸びる。慰めたいとか、優しくしたいとか、そういうことじゃなくて、私たちはただ娘の乱れた髪を整えるためにそれをしてる。いつか触れることを躊躇う日が来たなら、それが本当に蝶になって私たちの元から飛び立ってしまう日なのかもしれないと思った」

売野機子によるイラスト
■小谷実由(モデル)「わずか7歳の小さな少女が、葛藤しながらも懸命に立ち向かう姿。そして彼女が彼女らしく自由に生きることを望み、できる限り同じ目線に立ち、守ろうとする家族や周りの人々の温かさに希望を感じる。ラストシーンのサシャのはにかんだ笑顔がとても大人に見える。これからの彼女の心の平穏を願い、私には何が出来るのだろうと考えた」
■小林祐介(THE NOVEMBERS/THE SPELLBOUND)「今年小学生になった僕の娘は、毎朝自分の着たい服を選び、学校へ行く。好きな色の手提げ袋に、好きなキャラクターの水筒を入れ、好きな色の靴を履き、好きな色のヘアゴムで長い髪を束ね、学校へいく。彼女が選んだものを、誰かにとやかく言われることはない。“誰かにとやかく言われない”ものを徹底して選んでいるわけではなく、ただ自分の好きなものを、好きなように、身の回りに置いているだけ。彼女が、彼女自身としてただ存在しているだけ。誰のためでもなく、自分のために。そして、それが受け入れられる環境で、彼女は暮らしている。これは、幸運なことだろうか。それとも、普通のことだろうか。もうすぐ7歳になる僕の娘の境遇を、そしてサシャの境遇を“運”で片付けてはいけないし、“普通”で済ませてはいけない。彼女たちが、これまでもこれからも、心のままに生きていいということ。そして、心のままに生きる彼女たちが笑顔でいる環境を、育むこと、勝ち取ること。『リトル・ガール』はいま僕たちが住んでいる街の物語、僕たちの家族の物語です。どんな時も君の味方でいるよ、何があろうと君の味方でいるよ」
■雪下まゆ(イラストレーター)「カウンセリングのシーンでまだ幼いサシャが母親のことを気遣いながら涙を流すシーンには心が痛んだ。世の中のことをまだ知り始めたばかりの子どもが、なぜこのような思いをしなければならないのか、私たちは改めて考える必要がある」

雪下まゆによるイラスト
■大澤実音穂(雨のパレード)「特別な何かを求めているわけじゃない、ただ彼女らしくありのままを生きていたいだけ。そんなサシャがどうしようもなく愛おしい」
■haru.(株式会社HUG代表・アーティスト)「ただ、サシャが彼女自身でいようとすることを拒む大人たち。できる限りサシャの視線から撮ることを意識したというカメラワークは、彼女を幾度となく引き裂く学校の対応や言葉のもつ暴力性をありありと映し出す。サシャの小さな身体のなかで起きている爆発や震えが波動となって鑑賞者の私たちをも揺さぶる時、これは紛れもなく私とあなたの物語でもあることに気がつくのです」
■池辺葵(漫画家)「そっとでも触れないように慎重にうつしだされていくサシャの自我、忍耐、美意識……家族や制作者たちのまなざしがあたたかくてずっと日だまりを見ているようだった」

池辺葵によるイラスト
■今日マチ子(漫画家)「少女であるために、闘わなくてはならない。すべての人に、それぞれの普通があること。“当たり前の世界”はまだ遠い。でも、必ずたどり着けることもこの家族は教えてくれる」
■小林啓一(映画監督)「見ている間、ずっと涙が止まりませんでした。悪いものが全部でたというか、ものすごくあたたかいものに触れたというか。現代人が忘れがちなものを彼女たちは大切にしていて、それを他者に押し付けるわけでもない。ただただ人としての在り方に感銘を受けました。きっと、今一番大事にすべきものがみつかるはずです」
■小田香(映画作家)「もうすこし大人になれば、ちょっとは楽になるのかな。制服、トイレ、更衣室、履歴書、性別で区分けされたこの世界。親を悲しませたいわけじゃない。友だちを戸惑わせたいわけじゃない。サシャの瞳の奥に感情がうずまく。知ってるよ、その気持ち。懐かしいがまだ生きている痛みを思い出しながら、“ただ私でありたい”子どもたちや、親御さんたちに、サシャの姿が届くことを願った」
■やまじえびね(漫画家)「サシャの家族それぞれの語る言葉が胸を打つ。少しずつ差してくる光を見せてくれるこの映画は、貴重な家族の愛の記録だ」
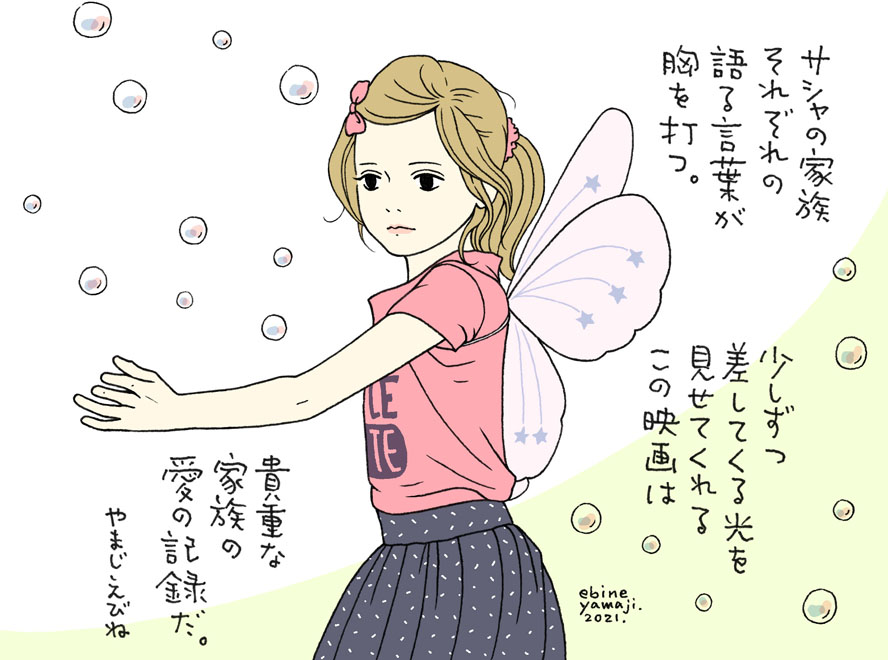
やまじえびねによるイラスト
■遠藤まめた(LGBT系ユースの居場所「にじーず」代表)「性的少数者と聞くと大人の姿をイメージしやすいけれど、実際には言葉を覚えたばかりの子どもが、自分の性別について悩むこともある。『こんなに小さい子どもが? 』『大人が誘導しているんじゃないの? 』日本でもそう考える人がいる。そんな人には、ぜひこの映画をみてほしい」
■草野絵美(アーティスト)「たとえ、まだ未熟でも、子どももひとりの人間で、独立した存在であることを忘れてはいけない。私も2児の親として、息子たちを”変えよう”としてはならないと改めて思った。サシャのような子が涙をながなくてもすむような社会にしていきたい」
■長田杏奈(ライター)「言葉少なで感情表現が控えめなサシャの瞳に、じわじわ溜まってやっとこぼれ落ちる涙。この涙に、大人や社会はどう応えるか。気にかけて耳を澄まさねば聞こえてこない小さな声を、かき消し踏みつけてはならない」
■多田由美(漫画家)「サシャとサシャのママはまるで親友のよう。共に戦い共に涙する。サシャの他の家族もまた結束が強く、父母に似てみな毅然としている。“普通”を振りかざして、幼い子どもが居心地のいい場所を求めてスカートをはくことを断罪する人たちがいる。サシャは声に出さずに戦い続ける。緊張が解けた瞬間の、はらはらと落ちるサシャの涙が胸を締め付ける」
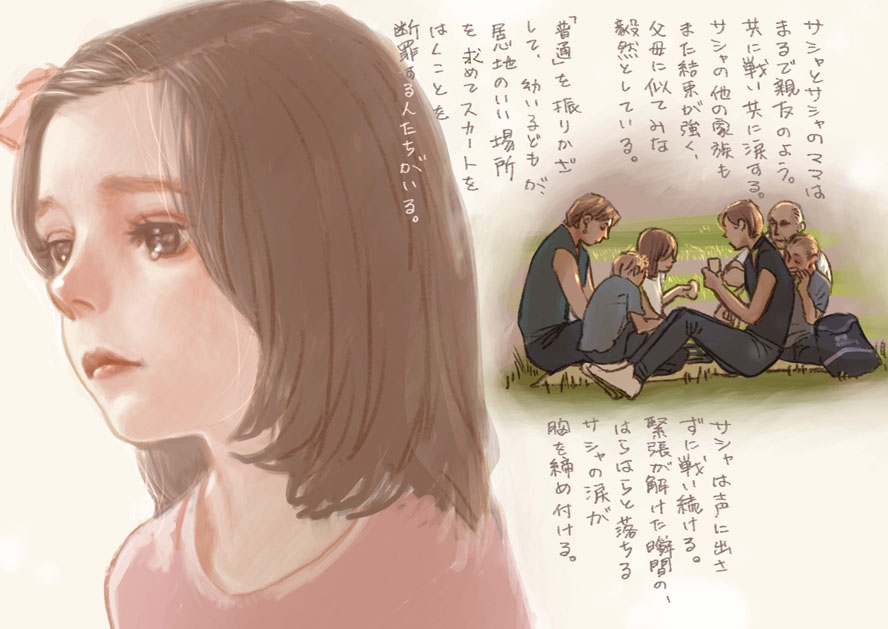
多田由美によるイラスト
■合田文(パレットーク編集長)「どこでも堂々と自分のジェンダー・アイデンティティを示すことができるというのは、決して当たり前ではない。少女の傷ついた心がにじみ出る悲しい微笑、母たちに心配をかけまいと紡がれる言葉が物語ります。独りで闘いに勝つことはできないかもしれない。『何をしても変わらない』とあきらめたくなるかもしれない。でも、家族がいたら。友だちがいたら。理解者がいたら。教育機関が変わったら。私たちはどの立場をとるべきなのか、考えさせられる作品です」
■福岡南央子(グラフィックデザイナー・アートディレクター )「差別する側の不可視。ちいさなひとの尊厳。子どもを映像に記録し広めることの責任。映画の持つ、変化を生じる力……。この映画が突きつけるものは何層にもなって、簡単に消化できず、もっと考えろ、学べ、闘えと自分に言うとき、光に縁取られたサシャの横顔がいつも浮かぶ」
■相川千尋(仏日翻訳・編集者)「思わずこぼれるサシャの涙は、『トランスジェンダー』『性自認』『性別違和』といった言葉の向こうに、生きて、泣き、笑う、ひとりひとりの人間がいることを思い出させてくれる。映画に出演したサシャと家族の勇気。受け止めた痛みを、社会を変える力にしなくてはいけない」
リフシッツ監督の洞察力に満ちたカメラワークが冴える
監督を務めたのは、これまでも社会の周縁で生きる人々に光をあてた作品を撮り続け、カンヌやベルリンを始め、世界中の映画祭で高く評価されているセバスチャン・リフシッツ。トランスジェンダーのアイデンティは肉体が成長する思春期に芽生えるのではなく、幼少期で自覚されることについて取材を始めていた過程で、サシャの母親カリーヌに出会い、この作品が生まれた。
この作品も、2020年ベルリン国際映画祭で上映後、モントリオール国際ドキュメンタリー映画祭のピープルズ・チョイス賞や、シカゴ国際映画祭国際ドキュメンタリーコンペティション部門シルバー・ヒューゴ賞、第33回東京国際映画祭ユース部門正式出品、第33回ヨーロッパ映画賞ドキュメンタリー賞ノミネート、第30回インサイド・アウトLGBT映画祭観客賞受賞など、世界中で様々な映画賞を受賞している。
また、コロナウィルス感染の影響により劇場が封鎖されたフランスでは、同年12月にテレビ局ARTEにて放送され、視聴者数1375000人、その年のドキュメンタリーとしては最高視聴率(5.7%)を獲得。オンラインでも28万回以上の再生数を記録するなど大きな反響を呼んだ。ドキュメンタリストとして確かな地位を築いたリフシッツ監督の洞察に満ちた繊細なカメラは、家族の喜びの瞬間、直面する多くの課題を捉え、幼少期の“性別の揺らぎ“に対する認知と受容を喚起する貴重なドキュメンタリー作品として実を結んだ。
『リトル・ガール』は11月19日より、全国で公開される。
PICKUP
MOVIE
INTERVIEW
PRESENT
-
【トークイベント付き】『エターナルメモリー』の一般試写会に10組20名様をご招待!
応募締め切り: 2024.08.09 -
【トークイベント付き】『コンセント/同意』の特別試写会に10組20名様をご招待!
応募終了: 2024.07.14




































