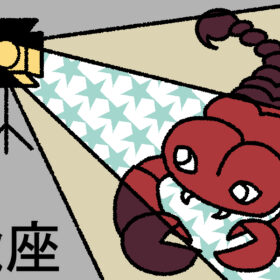1984年2月25日、鳥取県出身。2007年『仮面ライダー電王』で女優デビュー。『腐女子彼女。』(09年)で映画初主演を飾り、映画やドラマに多数出演。映画の主な出演作に『ペコロスの母に会いに行く』(13年)、『はなればなれに』(14年)、『駆込み女と駆出し男』(15年)、『GONIN サーガ』(15年)、『×××KISS KISS KISS』(15年)、『ディアーディアー』(15年)、『屋根裏の散歩者』(16年)、『無伴奏』(16年)などがある。
エリートサラリーマンの夫、美人で完璧な妻、そして可愛い一人娘という、絵に描いたように幸せな家族を襲った一家惨殺事件は、迷宮入りしたまま一年が過ぎた。週刊誌の記者である田中(妻夫木聡)は、改めて事件の真相に迫ろうと取材を開始する――。
ミステリー文学界の魔術師・貫井徳郎による第135回直木賞候補作「愚行録」の映画化に、妻夫木聡、満島ひかりをはじめ、小出恵介、臼田あさ美、市川由衣ら日本映画界を牽引する豪華実力派俳優が集結。原作者自ら、映像化不可能と語った小説を再構築し、人間の奥底にある、目を背けたくなるような感情を冷徹に描き出した問題作となっている。
本作でカギとなるのは、『ペコロスの母に会いに行く』『無伴奏』の松本若菜が演じる、一家惨殺事件で殺害された妻・田向友希恵(旧姓・夏原友希恵)。一見、華やかな世界に生きているように見えて傍目からは理想的と思われた彼女だったが、田中が証言者に取材していくうちに、次第にその理想とはかけ離れた実像が浮かび上がってくる。今回は、夏原友希恵という役柄で新境地を切り開いた注目の女優・松本若菜に、本作にかける思いなどを聞いた。
松本:何日もひきずってしまうような感じがありましたね。この映画のキャッチコピーには「三度の衝撃」と書いてありますが、三度どころか十度くらいの衝撃がありました。妻夫木さんがバスから降りる冒頭のシークエンスから、ひとりの人間性の怖さ、いやらしさなどが描かれていたのが本当に衝撃的で、背筋がゾッとしました。自分が出てるということじゃなく、本当にこの映画は2回以上見てもらいたい。脚本を読んで、内容を全部知っているはずの私ですら、映像を見て何度も驚いてしまう映画なんです。見終わってから本当に席から立てなかったですから。
松本:映画の脚本を読ませていただいた時に、原作と映画の脚本で描かれる夏原の違いを感じました。原作では、ママ友とのエピソードがあったりと、大人になってからの夏原がメインで描かれていました。しかし映画版では、大学という狭いコミュニティーの中で立ち振る舞う夏原が描かれていました。だからこそ、映画の脚本に描かれた夏原の方が、女としては理解できるなと思いましたね。
松本:女性ってグループを作りたがるじゃないですか。わたし自身は大学には行っていないのですが、小中高と学生を経験した中で、同じくグループを作るという経験はあります。そういう部分が描かれていたからこそ、映画の中の夏原の人間性というのが明確に見えてきて、面白いなと思いました。本当は分かりたくなのですが、女として分かってしまう、というようなことはありましたね。
松本:そもそも夏原って(私立の一貫校に)外部から大学入学したのに“内部生”的な存在となっていった人で、そういう意味ではすごくガッツのある女性ですよね。でも私自身は「マウンティング? ああ面倒くさい、やだやだ」と思うタイプなんです。
松本:夏原を、目線の動きや語尾の使い方などで悪い女性であるように見せることもできると思いますが、撮影に入る前から石川監督とは、「例え10人中8人が“夏原は悪いヤツだ”と思っても、少なくとも2人には、“夏原は本当に悪い人なのかな”と思わせるようなキャラクターにしましょう」と話し合っていました。かといって、まったく含みを持たせていないというわけでもなくて。やはり思うところがあっての笑顔や目線の動きだよね、ということはずっと監督と話し合っていて。そういった部分で何度もリテイクを重ねましたね。
松本:夏原って、ひとりひとりの証言者の中にある、思い出の中の女性なんですよ。ある人物からは「すごく気が使えてパーフェクトな女性」と言われていますが、違う人物からは「あんな悪い女は見たことない」と言われる。それぞれの人物にとっての夏原像があるんです。だからこそ、“本当の夏原というのはこういう人”だという芯となる部分は作らずに、それぞれの思い出の中のキャラクターでありたいという思いはありました。演じている時は大丈夫かなと思っていましたが、仕上がりを見てはじめて夏原ってこういう人なんだと知ることができたくらいなので。
──本作のメガホンをとった石川慶監督は、ロマン・ポランスキーらを輩出したポーランド国立映画大学で学んだ新鋭監督です。ポーランド仕込みの演出スタイルだったとのことですが、普段の撮影と違う部分は?
松本:プロデューサーさんから、石川監督はセッションを大事にする監督だからと言われて。撮影前に2、3回くらいミーティングをしました。ちゃんとひとりの人間として、しっかりと役を作り上げていくのが、ポーランドの作り方なんだとか。ただ、夏原という役については、石川監督も撮影がはじまってもずっと悩まれていました。撮影がはじまって、段取りが始まって、という段階になっても、さあ夏原をどうしようかと考えていくというのは、ポーランドではよくあることなんだそうです。とても新鮮でしたが、だからこそこの役が固まったというところがあったと思います。
松本:照明技師さんがおっしゃっていたんですが、日本では考えられない光の作り方をする人だと、ものすごく感動されていて。とても勉強になったとおっしゃっていました。
松本:そうですね。冷たい中にも、このシーンで赤のライトを使っちゃうんだ、と驚いてしまうようなところもあったんですけど、実際にそのシーンの映像を見たら、ものすごくカッコよかった。それはポーランド式なのか分からないですが、日本にはない技術があったと思います。
松本:監督と1からひとりの女性像を作りあげたのは初めてなので、すごく新鮮でしたが、仕上がりを見て、初めて私の代表作になるものができた、という思いがあります。私は2007年の『仮面ライダー電王』でデビューしているんですが、まわりの方からは、いまだにその印象が非常に強いようで。もちろんあのときは素敵なキャラクターをやらせてもらったし、いい経験にもなっているんですけど、そのイメージを覆したいという思いはありました。今年はちょうどデビュー10周年なんですが、そんなときにこの『愚行録』に出会い、違った側面を映像で残せたことはものすごくしあわせなことだなと思います。だからこそこういった日を迎えられて感無量です。
(text&photo:壬生智裕)
NEWS
PICKUP
MOVIE
PRESENT
-
【キャスト登壇】『キャンドルスティック』ジャパンプレミアに10組20名様をご招待!
応募締め切り: 2025.06.09 -
『秋が来るとき』特別一般試写会に10組20名様をご招待!
応募終了: 2025.05.22