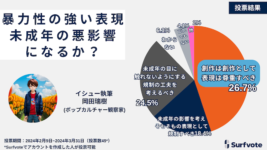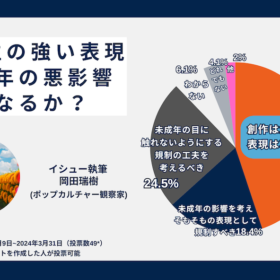1968年ハンガリー生まれ。過去11年間で150本を超えるCMを手がけた売れっ子CMディレクター及びプロデューサーとして活動する一方、過去6年間に10本の短編映画を監督。34の国内、外の短編映画祭で上映され、11の賞を獲得した。『リザとキツネと恋する死者たち』は初めての長編映画で、カンヌ、ローマ、サラエボなど多数の映画祭にて注目された。
『リザとキツネと恋する死者たち』ウッイ・メーサーロシュ・カーロイ監督インタビュー
日本LOVEな売れっ子CMディレクターが映画初監督!

ヘンテコな昭和歌謡が満載の、なんとも不思議なジャボネスク・ファンタジー『リザとキツネと恋する死者たち』。ハンガリーの売れっ子CMディレクターであるウッイ・メーサーロシュ・カーロイの長編映画デビュー作は、日本の那須に伝わる「九尾の狐」の伝説をモチーフにした摩訶不思議な作品だ。
舞台となるのは1970年代のブダペスト。日本大使未亡人の看護人として住み込みで働くシングル女性リザは、孤独な毎日を過ごしていた。心のよりどころは日本の恋愛小説と、リザにしか見えないユーレイの日本人歌手、トミー谷だけ。そんな彼女の周囲で奇怪な殺人事件が起こり始めるが……。
日本音楽の大ファンというメーサーロシュ監督に、映画について、そして日本文化への思いについて聞いた。
監督:実はそれほどハッピーな感じでもないんです(笑)。もちろん嬉しいですけど、人生というのは奇妙なもので。リザ役のモーニカ(・バルシャイ)は、実は僕のガールフレンドで一緒に暮らしているのですが、ハンガリーでこの映画のプレミア上映を行った頃に、動物シェルターから子犬をもらってきたんですよ。この子が居間にウンコしたりするのでそれを掃除したり、2時間ごとに散歩に連れ出さないとダメで、すごく手がかかる子犬で。寝不足だし疲れていたし、いろいろ絶賛のレビュー記事が出始めたのに、僕「素晴らしレビューが載ったよ」、彼女「あっ、そう」みたいな(笑)。でも考えてみれば、そういうふうに浮かれることなく地に足をつけて、監督デビュー作の成功を迎えることができたのも良かったと思います。
──日本音楽の大ファンで、本作に出てくる不思議な“昭和歌謡”は全て、監督がハンガリーの作曲家と作られたものだそうですね。日本文化が好きになった理由はあるのですか?
監督:もともと日本には興味があり、黒澤明監督や小津安二郎監督の映画も見ていたし、芥川龍之介や深沢七郎の小説も読んでいましたが、決定的な瞬間というのは寿司を食べた時なんです。27歳ぐらいの頃の話です。ハンガリー料理と寿司はまったく味が違うので、ハンガリー人にとっては奇妙な食べ物に思えるはずなのですが、私はなぜか頭に「故郷(ホーム)」という言葉が浮かびました。後にも先にも、何かを食べてそう感じたのはあの時だけです。まったく不思議でうまく説明ができないのですが、実際その経験が決定的でした。
もちろん音楽も好きで、ドイツでリリースされた「Sushi3003」「Sushi4004」というJ-PopコレクションのCDを聞き込みました。ちょっとアングラなポピュラー・ミュージックですね。もちろん、ピチカート・ファイヴのように有名なアーティストの曲も入っていましたが。なので、CDの「Sushi」コレクションと“フード”の寿司の両方に培われたという感じです。あと、夢にも日本が出てきました。1つ覚えているのが、私が神戸にいて、神戸の海岸で海女さんが牡蠣を海に潜って取ってくるといった内容。もう、これは日本に行かなくては!と思いました。
監督:小津安二郎監督の『東京物語』はもちろん感動的ですし、黒澤明監督だと『乱』や『七人の侍』、北野武監督の『HANA-BI』も好きです。『やくざの墓場 くちなしの花』などの深作欣二監督の作品は全部好きでコレクションしています。フリーズフレームでバンと字が出るスタイルは、全部深作欣二監督のやり方を真似していると言っても過言ではないです。あと、宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』『もののけ姫』も好き。彼の作品もある意味おとぎ話ですよね。
監督:実は東京でもオーディションをしました。15人ぐらい俳優に会いましたがピンと来なかった。トミー谷に必要なエンターテイナー、シンガーという雰囲気が今ひとつ足りなかったんです。もしかしたら、ハンガリーは貧しい国なので、オファーしているギャラが少なかったという理由もあるかもしれない。次に、スポンサー企業のひとつがデンマークにあるので、デンマークの俳優をあたりました。デンマークは韓国からたくさんの孤児が養子に迎えられているのですが、そんな中の1人で、デンマークの王室劇団に所属している俳優を当初はキャスティングしていました。でも、撮影日程の関係で出られなくなってしまった。振り出しに戻った時に、デンマークのエージェントから「日本人の俳優もいるけども会ってみないか」と言われ、紹介されたのがデヴィッドでした。彼は日本人とデンマーク人のハーフです。アクション俳優でもあってすごく身体を作っているし、いろんな格闘技もできる。彼で良かったと思います。情熱的に役に臨んでくれました。ダンスは未経験でしたが、日々ステップの練習を重ねて取り組んでくれました。
監督:実は結構複雑なキャラクターなんですよ。優しくて正直に見えながら、実は邪悪。裏では非常にネガティブなエネルギーを持っていて、怒りみたいなものを爆発的に表現できる、そういうトリッキーなキャラクター作りが重要でした。彼がかけているメガネですが、最初は実際に(コメディアンだった)トニー谷が使っていたような、もっと分厚くて黒い縁のメガネを考えていたんです。でも、それだと表面的な素直さのようなものが出ないし、派手なポップスターのようになってしまって、ちょっと違うと思いました。というのも、素直で正直に見えるという要素は、リザとの関係に説得力を持たせる上で非常に重要なのです。リザからすれば、彼のことがとても好きで、彼が邪悪な意思を持っているなんてまったく考えてもいないということを、観客にも説得力をもって伝えることが必要でした。
監督:あの頃のハンガリーでは、半永久的に使えるような丈夫なモノを作っていたと思うんです。この映画にも登場させているのが、ラジオやテープレコーダー。今でもああいうものを使っている方はいますし、私も使っています。(インタビュアーのICレコーダーを指差して)こういう最近のレコーダーは50年、60年この規格のままで使うことはできないと思う。
あともう1つ、いかに社会主義、共産主義の下で洗脳がうまく機能していたかという話になってしまうのですが、5歳の頃父の友人から「将来何になりたい?」と聞かれ、私は「ソヴィエトの兵士として英雄になりたい」と大まじめに答えました。父は恥ずかしい思いをしたそうです。でも、完全に見るもの、聞くものから洗脳を受けていたので、その言葉は本心でした。ただ、成長するにつれて色々な情報を得るようになり、16歳になった頃にはハンガリーの制度が変わらないのであれば、国の外に出たいと思うようにはなっていました。
監督:エンターテインメントでありつつ、メッセージ性のある作品を撮っていきたいです。動き始めているプロジェクトが2つあって、1つはテレビドラマのシリーズ。家庭内暴力を扱っているクライムストーリーです。ヘヴィーな題材なのですが、女性たちが暴力を受けたり、プレッシャーに晒されたときに何ができるか?ということを探っていくドラマです。もう1つは長編劇映画で、これもクライムストーリー。現在のブダペストを舞台にした連続複数殺人犯の話です。今日のブダペストの様子を正確に写し取りつつ、でもクライムストーリーとしては非常にクレバーで、かつ娯楽的側面もあります。大物でなくても人は英雄でなくてはいけないということを訴えていて、政治的なメッセージも含んでいるため、資金繰りが上手くいくかどうかの不安はあります。ただ、『リザとキツネと恋する死者たち』が成功したことをハンガリーの出資者たちは喜んでいますので、今、企画を出して返事を待っているところです。
監督:この映画には日本と関係のある要素がたくさんあるだけではなく、非常に普遍的なことを描いているので、日本の皆さんにも楽しんでいただけると思います。「愛」というのはピンク色の夢ではありません。愛を得るためには一生懸命努力しなくてはいけない。けれども、努力する価値のあることであり、努力すればご褒美をもらえるということを、この作品で伝えたいと思います。
NEWS
PICKUP
MOVIE
PRESENT
-
ユ・ヘジン&キム・ヒソン共演『マイ・スイート・ハニー』のオリジナルクリアファイルを5名様にプレゼント!
応募締め切り: 2024.05.05 -
【キャスト登壇】生田斗真×ヤン・イクチュンW主演『告白 コンフェッション』の完成披露試写会に10組20名をご招待!
応募締め切り: 2024.04.20